はじめに

最近、「認知症 過食」や「夜中に食べる 高齢者」といった検索が急増しています。この記事では、現役ケアマネジャーの立場から、家族が実践できる現実的な対応策をあらためて整理しました。
「過食」は認知機能の低下において、「一時的に」出てくる症状です。
「おばあさんが夜中になると、冷蔵庫を開けて中にあるものを全部たべてしまって・・・」
「おじいさんが冷蔵庫から生肉を食べていて…ため息がこぼれました」
この話は、実際にケアマネジャーで訪問したときに、在宅介護をがんばるご家族から聞いた話の一部です。
ご本人がしっかり食事をしたはずなのに「まだ食べたい」と何度も訴え、出した食事を次々と平らげてしまいます。
待っていただくように伝えれば、今度は冷蔵庫の中の食材を食べ始めます。
このような状況は、ご家族にとって心身ともに大きな負担となります。
さらにこの症状の難しいところは、この過食から、下痢症状も引き起こし、介護の手間がもっと増えてしまうことです。

この過食と下痢の両方の症状は本当にご家族様を悩ませます。
しかし、多くの認知症関連の本にこの症状の対策は載っていません。
私が知っている限り、「認知症の9大法則 50症状と対応策」という本には書かれていましたが、対応策は後述する一般的なもので、決定的な対策にはなっていませんでした。
本記事では、現役ケアマネジャーの私が知っている、認知症患者の過食の性質や原因、そして在宅介護でご家族が実践できる具体的な対策について解説します。

決定的な対策ではありませんが、実際に福行さんがご家族に行っていたアドバイスなども解説します。
この記事は、主任介護支援専門員の資格を持つ現役ケアマネジャーが執筆しています。在宅介護でお悩みの方に信頼できる情報をお届けすることを目的としています。
認知症における過食の性質と原因

神経学的な要因
認知症の方は、記憶障害により直前に食事をしたことを忘れてしまうケースが多く、実際には十分な食事を摂っていても「まだ食べていない」と感じ、何度も食事を求める傾向があります。
また、脳内の満腹中枢が正常に機能しなくなることで、通常の食事量で満腹感を得られず、必要以上に食べ続けることも原因となっています。

この辺りはよく認知症の本にも書かれていることですね。
そして、食べ過ぎが、下痢症状にもつながっていきます。
心理的な要因
認知症の進行とともに、本人は混乱、不安、孤独感を感じやすくなります。
こうした心理状態から、食事が安心感や慰めを提供する手段となり、結果として過食に結びつく場合があります。
さらに、衝動制御の低下により、目の前にある食べ物を我慢できずに摂取してしまうケースも少なくありません。

この我慢できなくなる衝動抑制の低下も認知症状の一つです
過食の現れ方
過食行動は個人差があり、日中ずっと食べ物を探し回る方もいれば、通常の食事時に大量に摂取する方もいます。

その人によって行動が違うんだね。

その人によってというよりは、対策によってという方が正しいかな。これはこの後に解説するね
多くの場合、過食の方は食事直後に再び「食べたい」と要求し、追加の食事や軽食を求めるパターンが見られます。
これを無視してしまうと、今度は、「異食」という行動を取る方もいます。
「異食」とは、食べ物ではないものを食べてしまうことをいいます。

過食、下痢、異食は避けることが難しいパターンです。
下痢が続くときは、必ず主治医やかかりつけの看護師に相談してください。
在宅介護における課題と家族の苦労
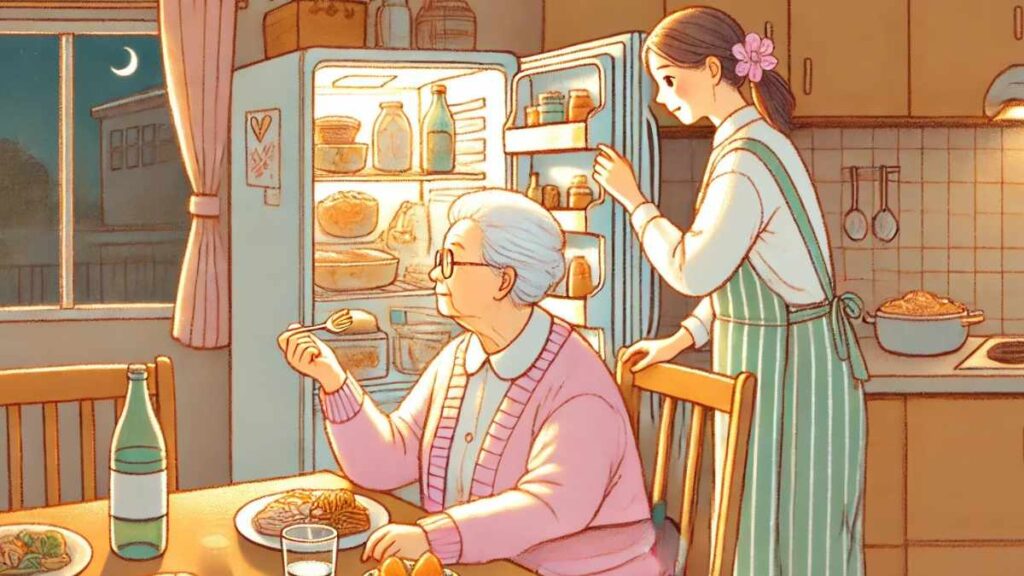
家庭内での食材管理の難しさ
在宅介護では、ご家族が食品の管理を行う必要があります。
冷蔵庫に食品が常に見える状態だと、本人の「食べ物があるから食べる」という行動を助長してしまいます。
そこで、一般的には、食品の保管場所や方法に工夫を凝らし、例えば
- 冷蔵庫に鍵をかけたり
- 透明でない容器に入れて見えにくくする
などの対策が知られています。
しかしそうすることで、その方が食べ物を探し回るという行動に出てしまうのです。

冷蔵庫の次によく狙われるのは、仏壇になります。

えっ?仏壇のお供え物まで食べてしまうの?

そうそう。
お供え物を片付けたとしても、今度は備えてあるあの砂糖の置物みたいな お供え物も食べてしまう方もいたみたいだよ。

(・・;)あれも食べちゃうの?

そうやって色々食べてしまうと、体内の消化も不十分になり、下痢を引き引き起こす原因になります。
家族間のストレスと心理的負担

もう食べたでしょ!
と、この様な否定をすると、本人は不信感や不安を感じ、さらに過食行動が激しくなることがあります。
そのため、家族全体が「これは認知症による症状である」と理解し、冷静かつ思いやりのある対応を心がけることが大切です。

教科書的に正しいのですが、ご家族様は、認知症の方と関係が近すぎるため、「認知症の症状である」という冷静な対応は思った以上に難しいです。

確かに目の前で異常な食欲で食べていて、それで

おばあちゃん
ご飯を食べていない
と何日も言われたら、冷静な対応なんてかなり難しいよね。

その上 認知症の方に対応するのは長男のお嫁さんとか、実の長女さんとか、意外と周りからの協力がなく一人で頑張っている方も多いです。

周りに家族がいたとしても、孤独を感じているなら、ストレスも溜まってしまうかもね…
家族で実践する在宅介護レベルの過食対策

ここからは過食に対する、よく知られている一般的な対策を挙げていきます。
ケアマネジャーの私もご家族様に実際にすすめてみて、どうだったのか、実際の声を聞いた評価になります。
おすすめ度を☆3つの評価で解説します。
★★★ 星3つ:おすすめの対応
★★☆ 星2つ:まあまあ効果あり
★☆☆ 星1つ:始めのうちくらいは効果あり
食事パターンの工夫
小分け食事の提供 ★★★
一度に大量の食事を与えるのではなく、1日の食事量を複数回に分けて提供します。
朝食、昼食、夕食に加えて、間食として軽食を用意することで、過食を防いでいきます。

この方法は摂取カロリーを抑える効果もあります。

小分けにすると 摂取カロリーが抑えられるの?

ご飯をあげる量をこちらで決めることができるから、ご家族が決めた量を小分けにすればいいので、食べ過ぎを防ぐことができるんだよ。
視覚的手がかりの活用
食後の食器を残す ★★☆
食事後、すぐに食器を片付けずテーブルに残しておくことで、本人に「すでに食事を済ませた」という視覚的な証拠を与えます。
これにより、再び食べ物を要求する行動をある程度抑制できます。

こちらもよく知られている対策です。
でもこの方法だと、空の食器を指さして

おばあちゃん
(# ゚Д゚)食器だけ持ってきてご飯どうして持ってこないんだ!
って怒る人もいるけどね。
具体的な時間の提示 ★☆☆
「今は○時で、次の食事は○時です」という具体的な時間を伝えることで、安心感を与え、無用な食欲を和らげる工夫も有効です。

介護職の人もよく知っている教科書的な対応方法です。
効果があるのは最初だけで、時間を伝えると

おばあちゃん
(# ゚Д゚)そんなに待ってられるか!
って徐々に我慢がきかなくなる傾向にあります。
安全な環境の整備
食品が見えないよう保管 ★☆☆
食品が目につかないよう、冷蔵庫やに鍵をかけたり、食品を透明でない容器に収納するなどの工夫を行いましょう。これにより、本人が不用意に食品に手を出すリスクを減らせます。

どうしてこの方法は 星ひとつなの?

これもよく知られている方法だけれど、冷蔵庫に鍵をかけてしまうと、少し変わった行動をするようになるんだよ。
冷蔵庫に鍵を取り付けると…

おじいちゃんの場合は、家にある大工道具のようなものを持ち出してその鍵を壊そうとしたりします。

おばあちゃんの場合だと冷蔵庫の近くのリビング や 食卓に張り付くようになります。

張り付いてどうするの?

経験的に冷蔵庫に食べ物があるのを知っているので、鍵が開いていて、なおかつ 誰もいない時をじっと待ってるんだよ。

そんなタイミングなんてある?
例えば
- ご家族が料理をしていて、突然電話が鳴って対応するとき
- 宅急便屋さんが来て対応するとき
- お手洗いに 行ったとき
そういう隙をずっと待っています。

そして 隙を見せると冷蔵庫の中のものを食べてしまいます。

それじゃあ 料理を作ってる時も気が気じゃないね(;_;)

冷蔵庫に鍵をつけても、安心できるのは初めの1〜2週間ぐらいでしょう。

食べ物を厳重に管理してしまうと、今度は異食に出るかもしれないので、難しいですね。
危険物の管理 ★★★
薬や洗剤など、誤って摂取すると危険なものは必ず手の届かない場所に保管し、安全面に配慮します。

食べ物をしっかりとブロックされてしまったから、口に入れられそうなものは何でも入れてしまう危険があるんだね。

異食に関しては、命に関わる危険もあるので、注意したいところだね。
仏壇のお供えの変更 ★★★
冷蔵庫の次に狙われるのは、「仏壇」です。仏壇のお供え物は、模型のものに変えたほうが無難です。

まさか・・・と思うけど、本当に食べるかもしれないんだね・・・

模型まで食べられたというのは、これまで聞いたことはないって福行さんが言ってたよ
柔軟な対応
健康的な軽食の用意 ★★★
もし本人が「まだ食べたい」と訴えた場合、否定するのではなく、少量の健康的な軽食(例:おにぎり、カットフルーツ、ヨーグルトなど)を提供し、安心感を与えながら過剰なカロリー摂取を防ぎます。

塩分に注意しながら、お漬物もいいですよ。

どういうことなの?

過剰に食べ物を摂取すると、下痢を引き起こす危険性があるから、なるべく 繊維質のものをとってもらって、消化器を守ろうとするんだよ。

また、かむことも促せるから、認知機能が低下してるなりに脳に刺激を与えることもできます。
柔軟なコミュニケーション ★★★
「もうすぐおやつの時間です」と具体的に伝え、家族の温かい声かけで不安を和らげることも重要です。

この声かけよりもっと効果的な関わり方があります。

それは何?例えばもっと時間を具体的に伝えるとか?
「おやつまであと8分52秒です」みたいな感じ…?

全然違うよ。

お茶やおやつの時間を一緒に楽しく過ごすことだよ。

(´・ω・`)それだけでいいの…?
在宅介護では、介護を受けるご高齢の方と、ご家族様は、意外に接点が少ないものです。
介護保険のサービスを使うと、なおさらサービスに任せてしまうため、一緒に関わるという機会は実は少ないのです。
そのため、お茶の時間などを一緒に過ごし、テレビを見て談笑するとか、楽しく過ごすと、実は空腹をあまり訴えずに、穏やかに部屋に戻って寝てくれたと、私の関わったご利用者様のご家族から何件か聞いています。

過食の原因に寂しさなどもあったから、確かに楽しく過ごせば 寂しくなんかないもんね。
気晴らしと活動の促進
食後の気分転換 ★★☆
食事後に短い散歩や音楽鑑賞、写真鑑賞などの気晴らしの活動を取り入れることで、過食への執着を他の楽しい活動へとシフトさせる効果が期待できます。

つまり ここでのポイントもご家族と一緒に過ごすということになります。
おじいちゃんおばあちゃんだけにさせてもあまり効果は出てきません。
参加型の家事 ★★☆
可能であれば、本人に簡単な家事(テーブルセットなど)を手伝ってもらうことで、自己効力感を高め、余計な食欲を紛らわせる方法もおすすめです。

こちらもご家族と一緒に行うということが ポイントです。
一方的にお願いするのはあまり効果がありません。
心理的サポートと家族自身のケア

認知症患者の過食に直面すると、家族自身も大きな心理的負担を感じるものです。
以下のことに留意して、家族全体でサポート体制を整えましょう。
家族間のコミュニケーション ★☆☆
介護の苦労や悩みを家族で共有することで、孤立感を解消し、共に支え合う環境を作ります。

それができるのだったら、そもそも 在宅介護の負担だって分散されて メインで介護する長男の奥さんや 長女さんとかはもっと気持ちが楽になるんじゃないの?
自己ケアの実践 ★★★
ご家族自身の心身の健康も非常に重要です。十分な休息やリラクゼーション、趣味の時間を持つことで、介護ストレスを軽減し、前向きな気持ちで介護に取り組むよう心がけましょう。

特に自分の親を介護する長女さんや 介護を受けるご高齢の方の配偶者の方などは、気負わずにしっかりと休んで欲しいですね。
専門家への相談 ★★☆
認知症介護の専門家、栄養士、作業療法士などのアドバイスを受けることで、家族だけで抱え込むことなく、より適切なケア方法を見つけることができます。

初めは 知らないことも多いから効果的な部分はあります。
だけどアドバイスも出尽くしてしまうと、相談しても解決ができないことが増えてきてしまいます。
簡単にここまでのまとめ

認知症高齢者の「過食」は、記憶障害や脳の満腹中枢の低下、さらには心理的要因が絡み合った複雑な症状です。
在宅介護においては
- 家族が食べ物収納の環境の見直しと整備
- 3食以外の食事を準備したり、繊維質があるものや低糖・低カロリーの食事の見直し
- 空いた食器を置いておく視覚的手がかりの活用
- 楽しい時間を一緒に過ごすなどの柔軟なコミュニケーション
- 食後の気晴らしの工夫
などなど、さまざまな対策を実践することが求められます。
これらの対策は、必ずしも完璧に過食行動を抑制するわけではありません。
しかし、できる範囲で行っていただくことで、健康リスクを低減し、家族自身の負担を軽減する上で大きな効果が期待できます。
ケアマネジャーができること

これまでのお話の通り、おすすめはあったとしても、どの対策も決定的に効果があるものではないので、過食ではご家族様のメンタル面が削られてしまいます。
そうなると、ご高齢の方に「怒り、いらだち」また、「不安や心配」などを抱えながら関わるようになってしまいます。
このような状況でケアマネジャーとしてできることは、デイサービスやショートステイを利用いただき、ご家族の休息や自由の時間を確保できるようにしていくことになります。
とくにショートステイの利用にはつなげていきたいと考えます。

どうしてショートステイなの?デイサービスではダメなの?

デイサービスもダメではないけど、
結局、おじいちゃんおばあちゃんが夜中に食べ物をさがし始めたりすることもあるから、
ご家族様が休む時間も確保するためにはショートステイの方がいいということです。
ショートステイには「レスパイトケア」の一環としての要素もあります。ご家族の休息は在宅介護の生命線と言っても過言ではありません。
「過食」は認知機能の低下において、「一時的」に出てくる症状です。
つまりこの時期をうまく乗り切れば、症状は落ち着きます。
私の経験上、過食状態で風邪や肺炎、心不全などで、一時寝込んだり、入院したりしたあとにも治まっているように感じます。
ですが、本当にやっかいのは、このあとにやってくる症状かもしれません。
過食のあとにやってくる症状

過食の対策でさんざんがんばってきたのに、そのあとがやっかいって、もうご家族さんも大変だよ…いったい何がやってくるの?

過食のあとにやってくるのは「拒食」です。

拒食…?今度は食べなくなっちゃうということなの?
常に過食から拒食にすすむわけではありませんが、私が受け持ったご利用者様でこのパターンは何名かいらっしゃいました。
拒食は、過食のときのような食べ物を隠したりとか、準備したりという慌ただしさはありません。
ですが、何食も食べない様子を見ていくと、急にその方の人生が幕を引くのではという不安が起こり始めます。
過食から拒食へ、その対策は・・・?
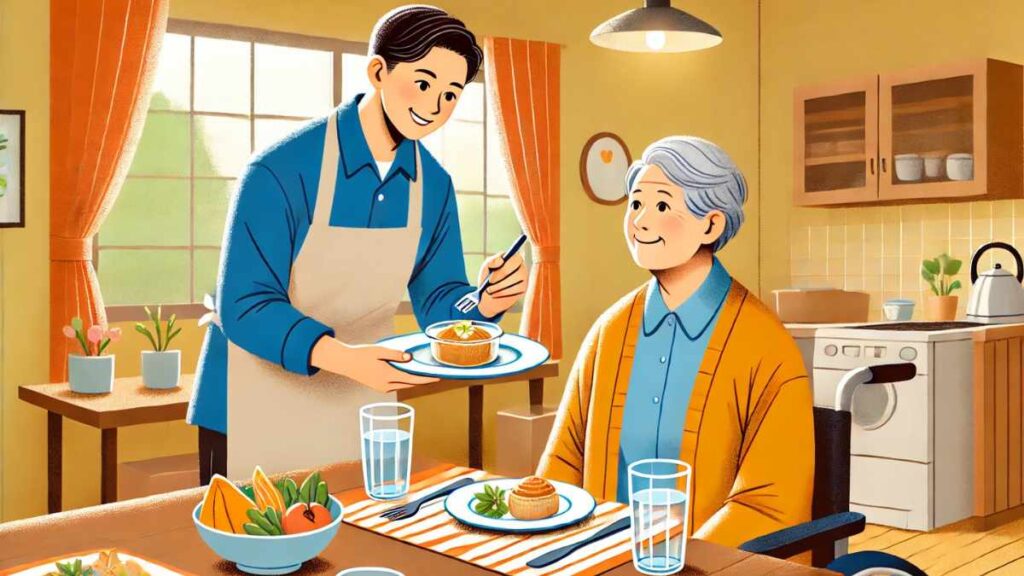

福行さんがこうして記事にしているのだから、何か対策はあるのでしょう・・・?
残念ながら、拒食も決定的な対策はありません・・・。
もちろん、拒食の原因は、口の中の痛みや誤嚥、便秘、薬の飲み合わせなどによる体調不良の可能性もあります。こちらは医師と相談して対策ができることがあるかもしれません。
ですが、認知機能の低下が進行している場合、
- 食べ物であるという認識ができなくなる「失認」
- 無気力・無関心状態や抑うつ状態によって食欲が減退し、食事に興味を示さなくなる「アパシー」
と呼ばれる症状がでていることが、拒食の原因になっていることが多いです。
こちらの場合は、対策がありません・・・。

でもさ、それでも頑張って、香りや風味よく彩りよく作って「おいしいよ」と優しく声をかければ、食べてくれるんじゃないの?
たしかに、食べてくれます。
熟練の介護職の方も上手に声掛けして食事介助をします。
しかし、常にテクニックでカバーはできず、いずれどんなに声掛けしても食べなくなってしまいます。
むりむり食べさせてしまうと、ますます食べることが嫌になるので、本当に難しいです。

(;O;)そんなぁ…じゃあどうすればいいのさ
ここで過食の時に行っていた楽しく過ごすというコミュニケーションが効いてきます。
楽しく会話をする中で、
- 良い関係性を築く
- その時に聞いた好きな食べ物や食べてみたい料理などを出してみる
- 関係性が良ければ食べなくなった後でも食べてみたいものは何かと聞く(教えてくれることがあります)
など、関わりのヒントも出ることがあります。
しかし、教えてくれた料理を出してみても食べないかもしれません。
ですが、 何も食べてくれないと不安を抱えるよりは、本人から聞いて食べたいものを出している分、すこしは気持ちが軽くなります。
いずれにしても、食べてもらえないといよいよ 人生の終着駅に向かうことを想像してしまいます。
食べ物の工夫をしながらも、楽しい時を過ごし、 最期かもしれないの時をご本人もご家族様も穏やかに迎えることを願うばかりです。
「食べなくなる」という変化は、どうしても「命の長さ」や「どこまで医療的に頑張るのか」といったことも考えざるをえない場面につながっていきます。
そこまで考えるのはつらい…という方は、この部分は今は気にしないでください。
もし、ご本人の『命の質』と『命の長さ』について、少し先のことも考えてみたいと思われた方は、こちらの記事も参考になるかもしれません。
おわりに
今回の記事では、認知症患者の「過食」の性質や原因、そして在宅介護における具体的な対策について、家族が実践できる方法を詳しく解説しました。
記憶障害や脳内の満腹中枢の低下、さらには心理的要因によって、過食は「一時的に」現れる症状です。

過食は「一時的に」現れる症状です。ずっとは続きません。
ご家族が
など、多角的な対策を実践することが、日々の介護のポイントとなります。

食品の保管を徹底しすぎると、今度は「異食」へ向かう方もいるので気をつけてください。
一方で、「拒食」は人生の最期にかかわる問題となる可能性もあるため、対応には、これまでの関わりの積み上げがポイントになってきます。
うまく関われば、ご本人が分からないなりにも分かってくれていると、ケアマネジャーとしてこれまでの経験で感じます。
過食と拒食はとてもやっかいな症状です。
どんなに困難な状況でも、ご家族様の努力と温かい支えが、ご本人の笑顔や安心につながり、ひとときの平穏をもたらすと信じています。

ご家族さんにはどうか、自分自身も大切にしながら、介護の日々の中で少しでも心に安らぎがありますように
おまけ:新章の予告です。

今回のお話しからも分かるように、介護を受けるご高齢の方との「関わり」がどのような状況になっても重要になってきます。

でもさ、ご家族とご本人の関係が近いと、これまでの関係性もあって、突然あたたかい関係なんて作るのむずかしくない?
身体もお仕事でクタクタなのに、家でも自分を出せず優しく振る舞うなんて、休む時間がどこにもなさそう・・・

本当に在宅介護はその中心でがんばるご家族の健康や気持ちの安定性が大事になります。
今回の過食・拒食への対応は、「知識」だけでなく、支える家族のメンタルケアが土台になります。

そこで新章はその「メンタル」面について書いていこうと思います。
新章は「かいごのメンタル」編になります。

これらに続く、最終章になります。

(。・_・。)最終章…。
とうとうここまで来たんだね…。
それで「かいごのメンタル」ではどんなことを書くの?

在宅で介護をしていく中で、ご家族に精神的にストレスが溜まっていく状況を少しでも軽くなることを目的とします。
これまでの利用者様やご家族との多くの関わりの中で、実際に聞いたこと、どのように精神的にまいったときに切り抜けてきたかを私なりにまとめて書いていきます。
在宅介護では、ご家族様はご高齢の方に対して「もう少しこうなってくれればいいのに・・・」と考えることもあると思います。
ですが、実際はご高齢の方に変化を求めるのは難しく、結局ご家族に変化を余儀なくされることは多いと思います。

結局変えられるのは、自分自身ですので、大変な状況を考え方を変えて、ストレスを軽くしてほしいです。

かいごのメンタル編で、在宅介護をがんばる方の気持ちが少しでも軽くなること願うばかりです。
ではサニー新章に向かって最後の締めをお願いします。

介護をがんばる皆さまのココロが晴れやかになりますように!
この記事の信頼性
本記事は、現役の主任介護支援専門員である筆者が、実際の支援現場で得た経験やご家族との関わりをもとに執筆しています。
内容の正確性を期すため、以下の公的機関・医療介護専門サイト・学術資料を参照しています。
- e-Nursing Care ガイド Q&A
- 認知機能セルフチェッカー コラム
- 介護の本音:認知症の質問
- e-Nursing Care ガイド:認知症の食事トラブル
- ALSOK 介護ブログ
- Homes介護マニュアル:認知症の食事症状
- 日本経済新聞 ビジネスレポート
- みんなの介護サイト:認知症サポート
- Sa-iwaicl.jp 論文PDF
- Miura Medical Clinic ブログ
- 健達ねっと:認知症と過食の解説
- Asahi Life 介護活動コラム
- アルツハイマー協会公式サイト
- J-STAGE 論文: Neuropsychology
- みんなの介護:認知症の進行について
- 日本経済新聞の記事
掲載内容は、2025年時点での介護・医療動向をもとに構成しています。今後も必要に応じて情報を更新し、より正確で現場に即した内容をお届けします。
内容に誤りや改善点がある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
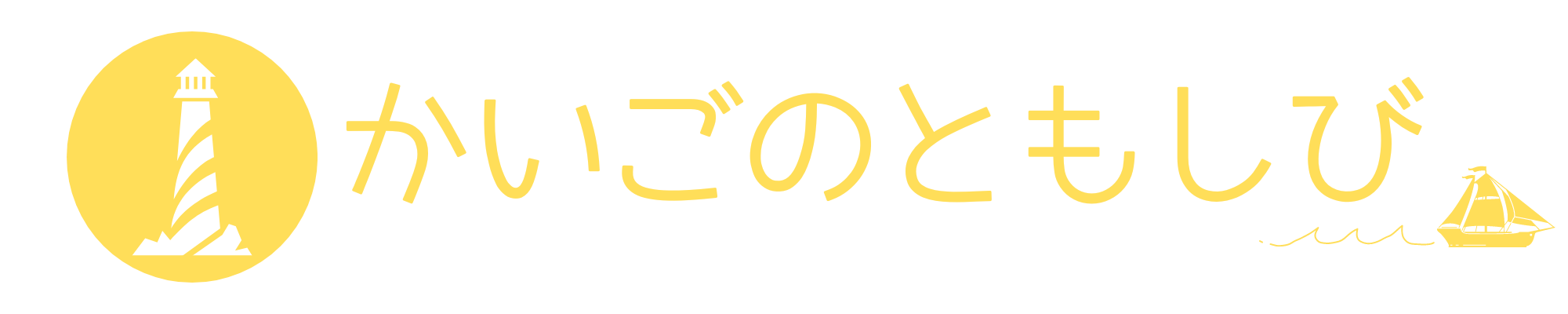
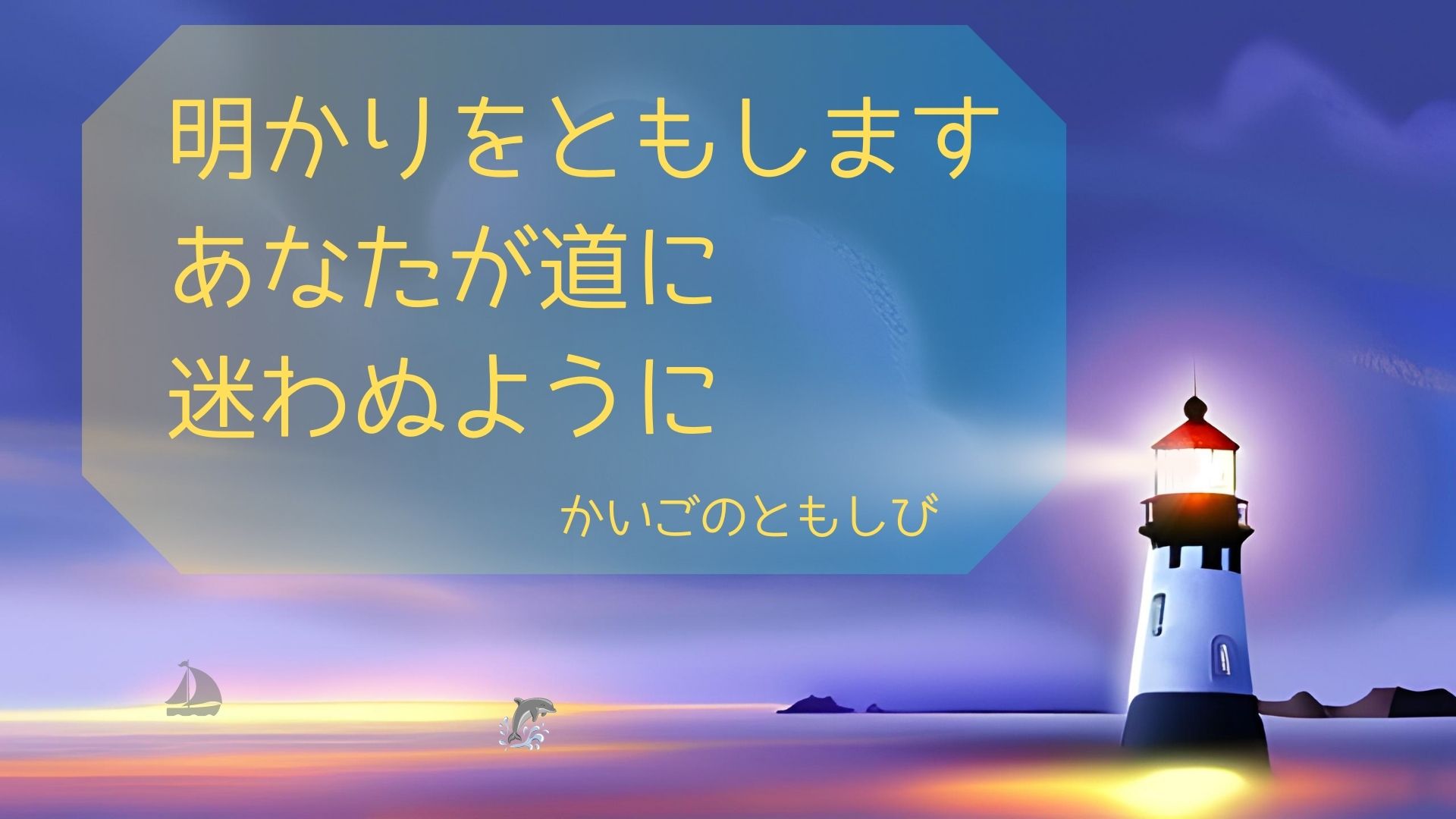

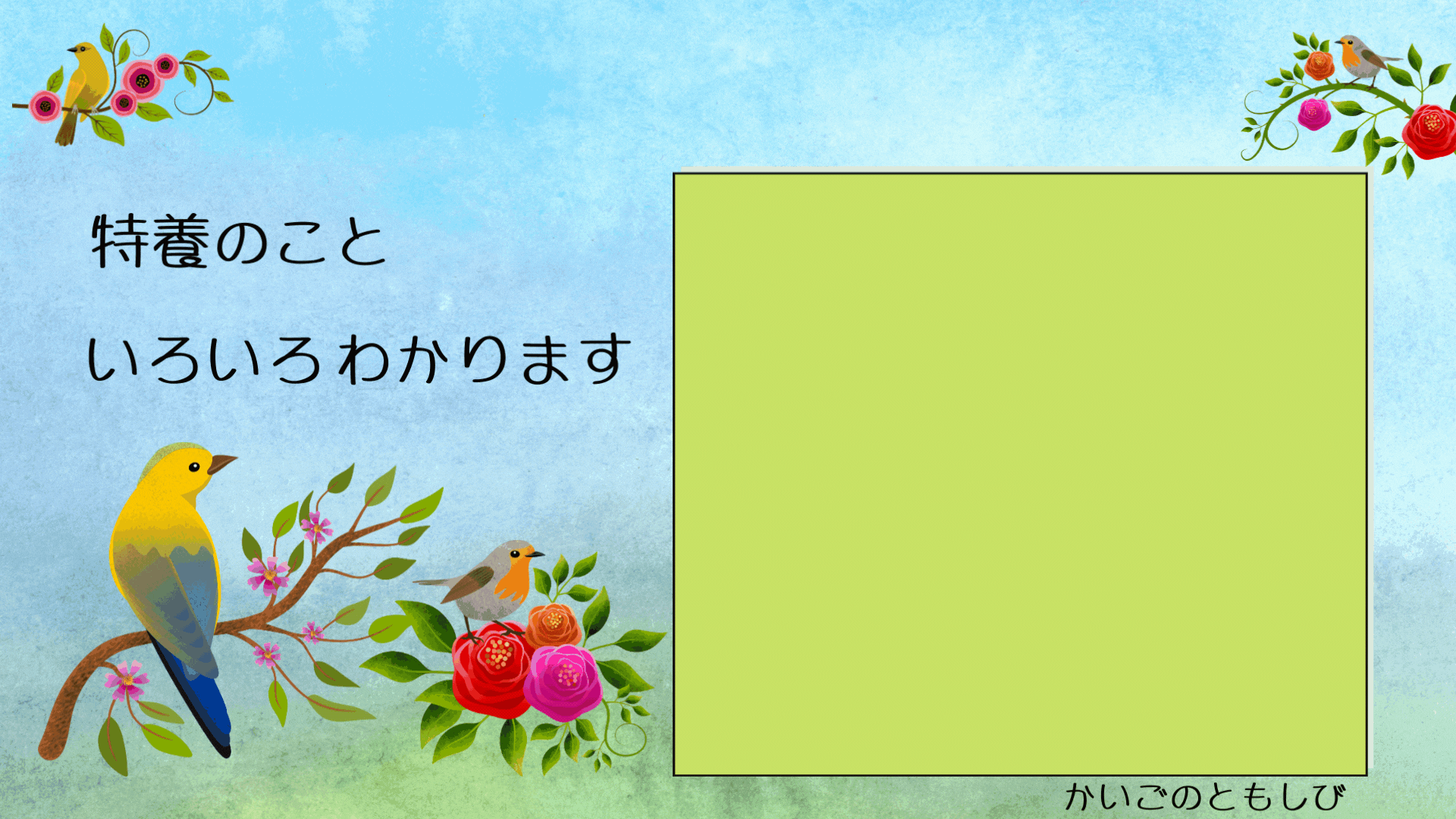



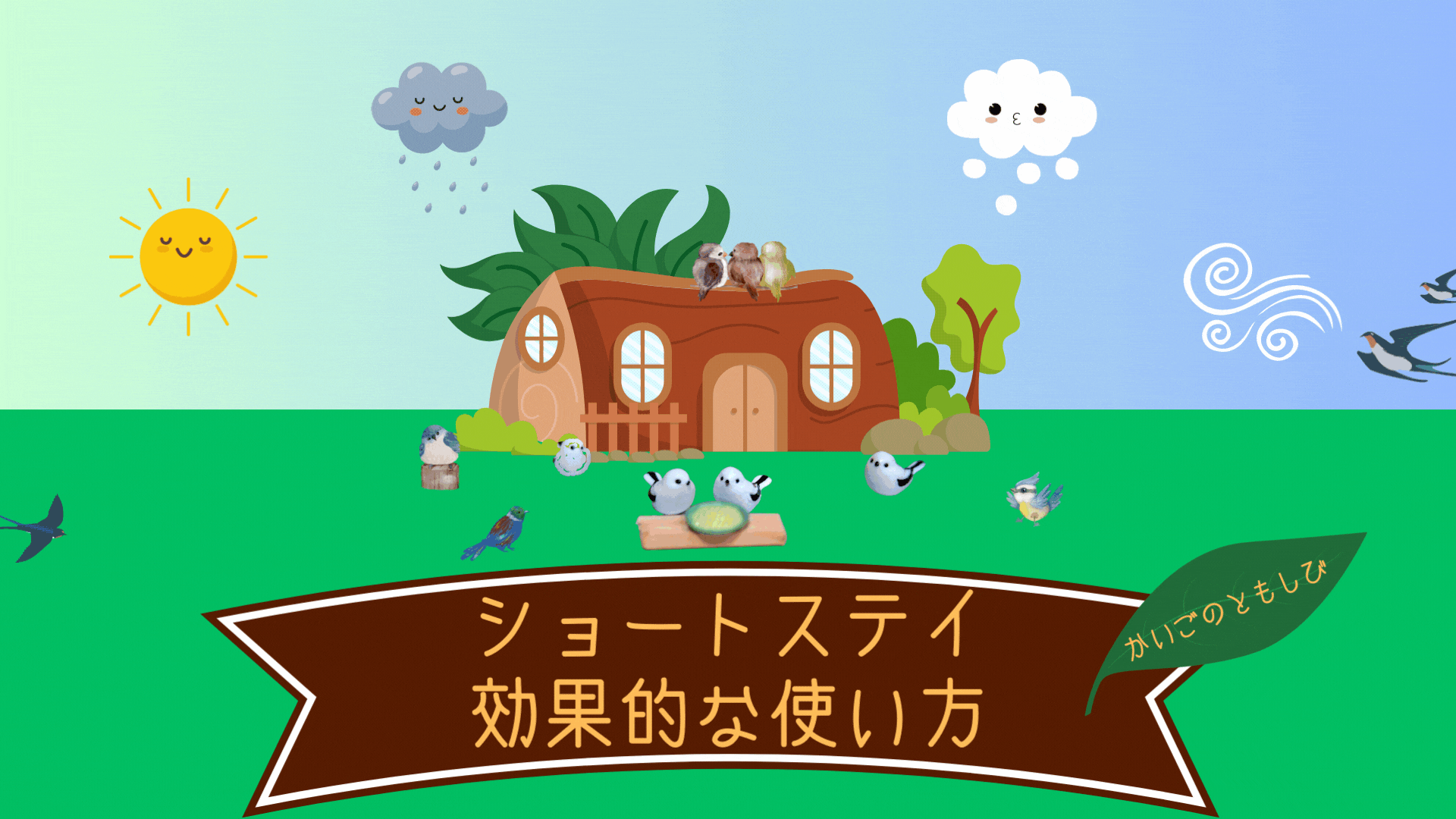




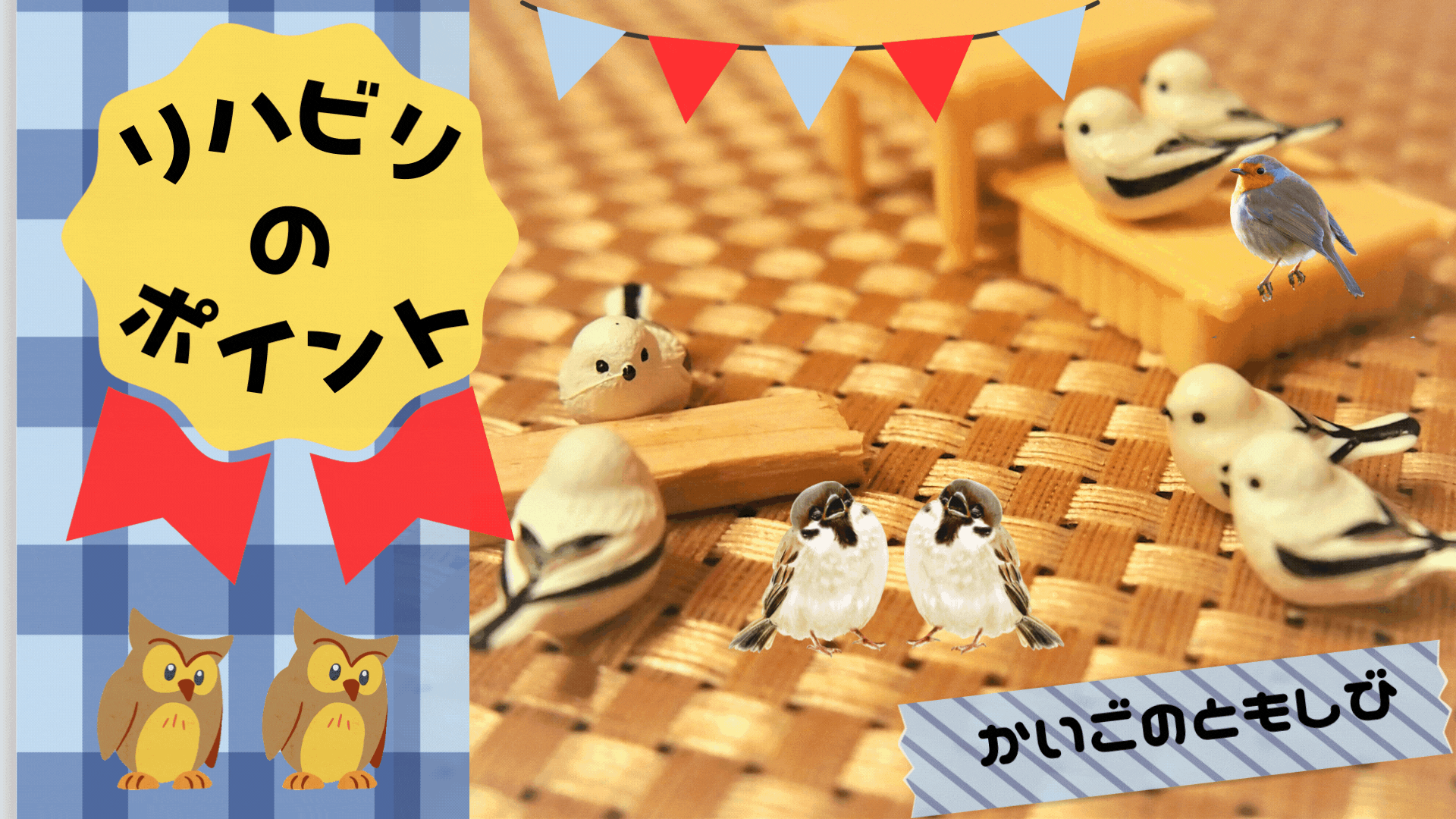

それはそうだよせっかくのご飯をみんな食べられちゃ大変だよ!