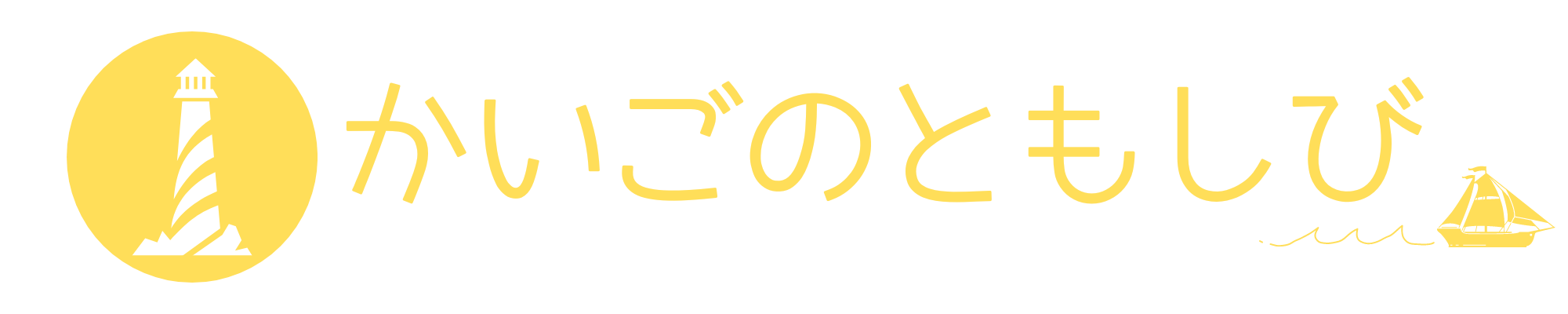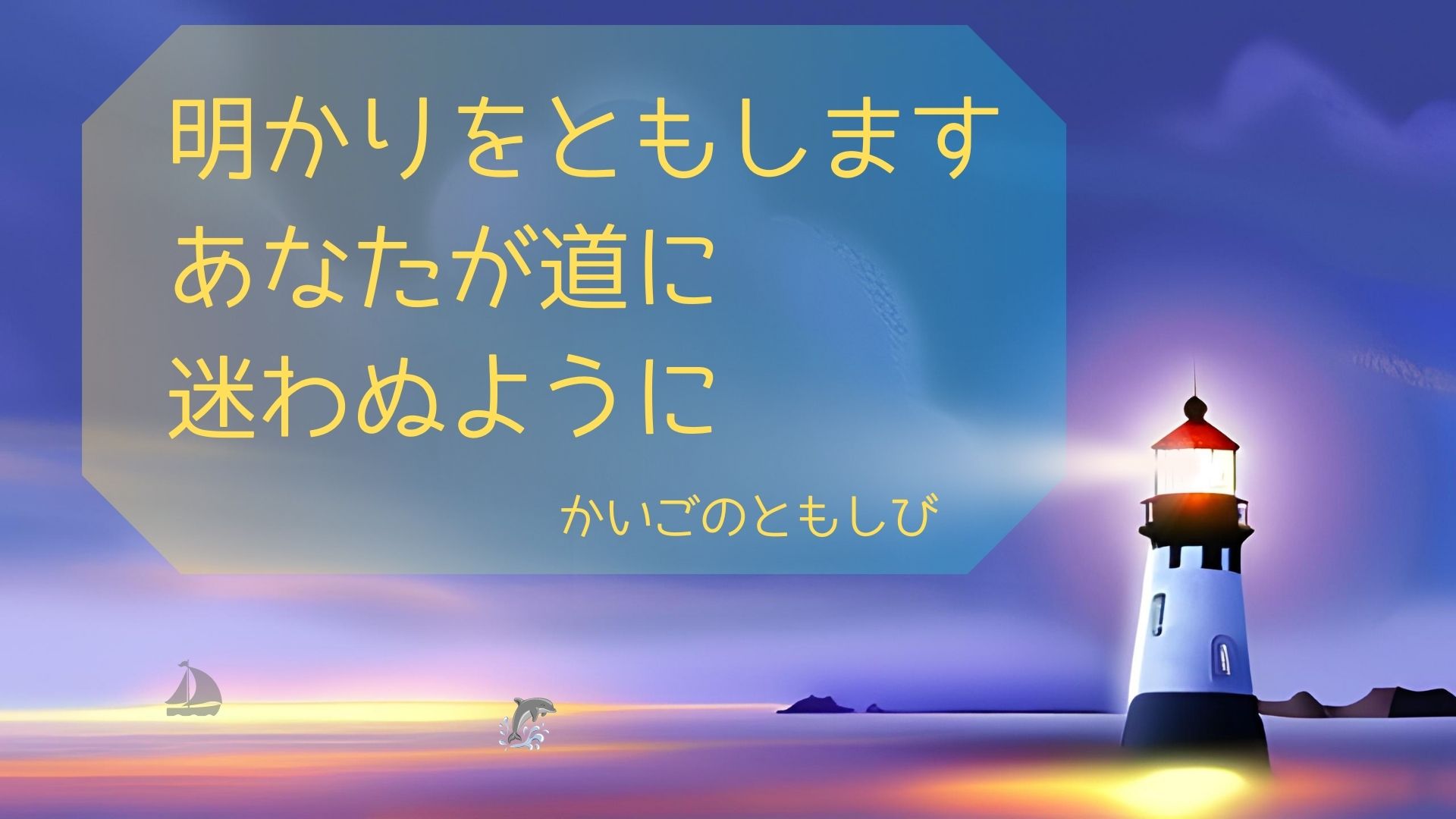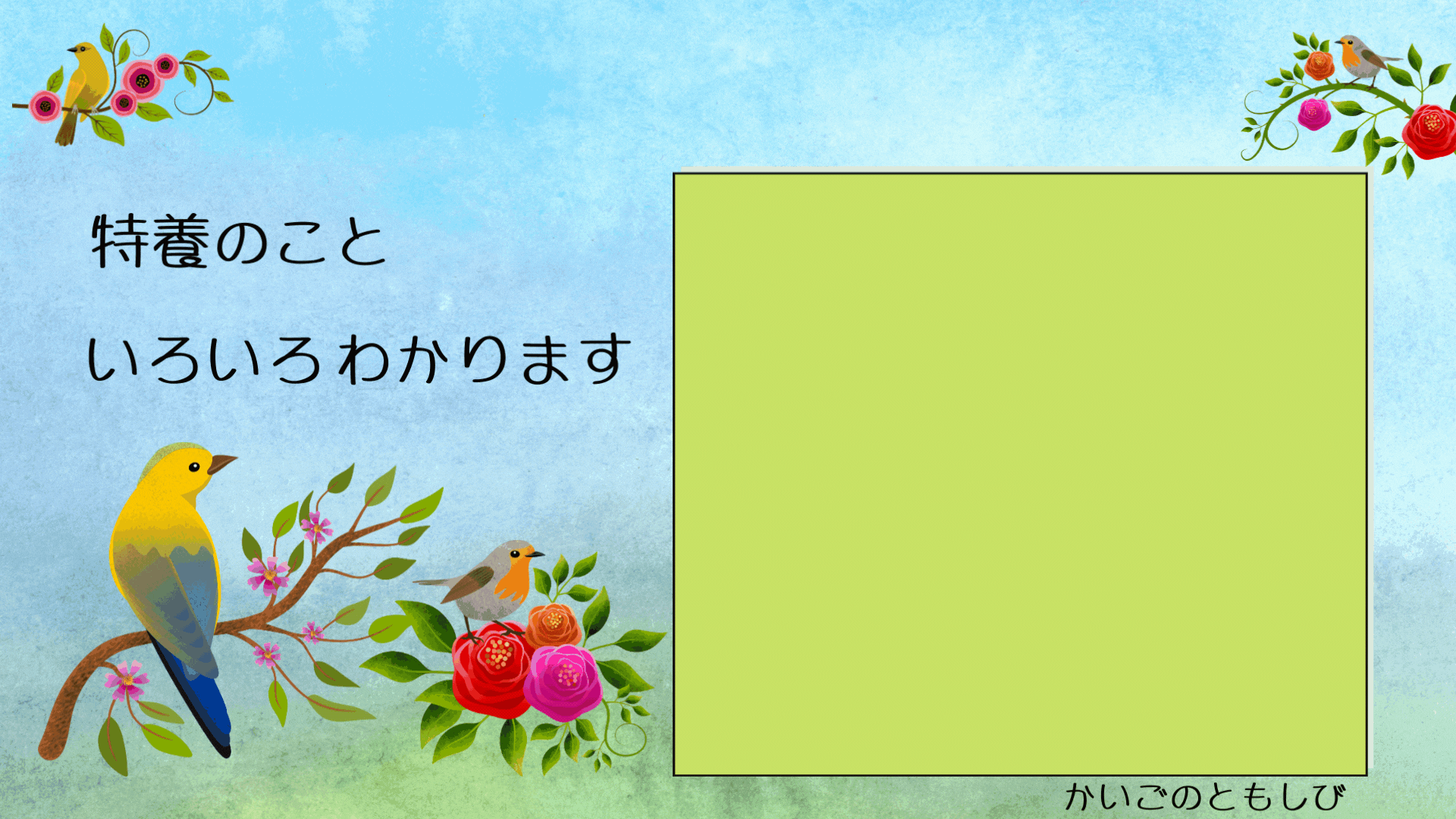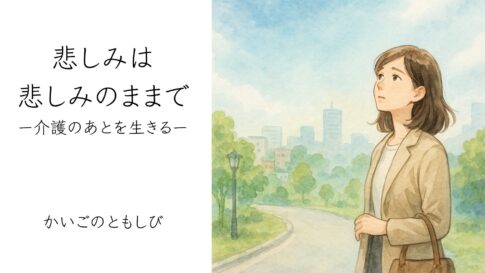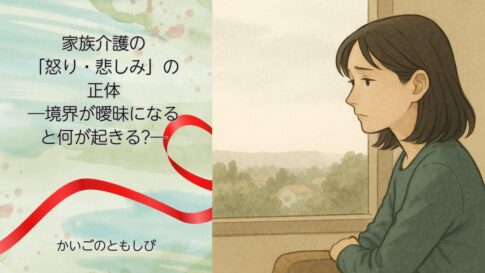はじめに:命が終わるかもしれないという現実と向き合うとき
もう助からないかもしれない…
お別れも近いと聞いた。
たしかに前のような元気さはないかもしれない。
けれど…
なんとかまた元気になることはできないのだろうか?
なんとか長く生きることはできないのだろうか?
本当にこのまま、最期を迎えるのだろうか…
それは、わたしのせいなのだろうか…
私が頑張れば、なんとか生きることはできないのだろうか?
がんばって、がんばってここまで来たのに…

がんばってきた介護
「終着駅」が見えてくると聞いたとき、安堵ではなく不安が胸をよぎります。
介護が始まり、自分の人生にうまく溶け込ませながら進んできて、その介護から解放されるはずだった。
なのに、最後は介護にしがみついて、介護を続けようとします。
「介護」は、元気になっていくというより、どちらかといえば、終着駅に向かって穏やかに到着していくようなイメージです。
つまり、介護を始めれば、必ず終わりがあるということになります。
終わりが近づくにつれ、介護をがんばるご家族様は「なんとか生きていてほしい」と願う気持ちが生まれます。
今回はこの問いについて、一緒に考えていきたいと思います。
この記事は、主任介護支援専門員の資格を持つ現役ケアマネジャーが執筆しています。在宅介護でお悩みの方に信頼できる情報をお届けすることを目的としています。
「長生きしてほしい」という気持ちは、誰のため?

介護者にのしかかる責任の重さ
あなたの人生の中に突然現れる「介護」。
始まりはあまりにも理不尽です。
さらに理不尽なのは、本来であれば家族みんなで支えていかなければならないのに、支えているのがあなただけという状況が多いことです。
つまり、「責任」があなただけに背負わされているように感じてしまいます。
介護に関わろうとしない家族は、その方の長生きを望みます。
しかし手は出しません。
介護に携わるのは、あなただけなのです。
そして、あなたは、その外野の家族の期待を一身に背負い、そのご高齢の方を必死に介護します。
命をつなぐ介護の重み

いわゆる「三大介護」と言われるもの(食事・排泄・入浴)は、その日、生きていくために必要なことです。
介護に手を抜いてしまえば、その方の生活の質が下がってしまいます。
それはすなわち、命を縮めてしまう可能性もあるのです。
病院のような医療機関であっても、治療以外で行われることは介護です。
つまり、介護をしっかり行うことは、生きていく上でのベースを整えることになります。
「これって本人が望んでること?」と思う瞬間

私たちが普通に生きていく中でも、ご飯を食べたくない日だってあります。
- 全く食べない日
- 少ししか食べたくない日
- 今は食べたいと感じない日
いろいろありますよね。
自分が食べたくない時に、もし無理やり「食べて」と言われて口に押し込まれたら、きっと嫌な気持ちになるはずです。
もし、誰かのお食事の介助をしているとき、それはただの作業になってしまっていませんか?
「食べたくない」と言われたとき
次のひとさじをすすめるその手は
何を目的にしているのでしょうか?
“その人らしく”生きるということ
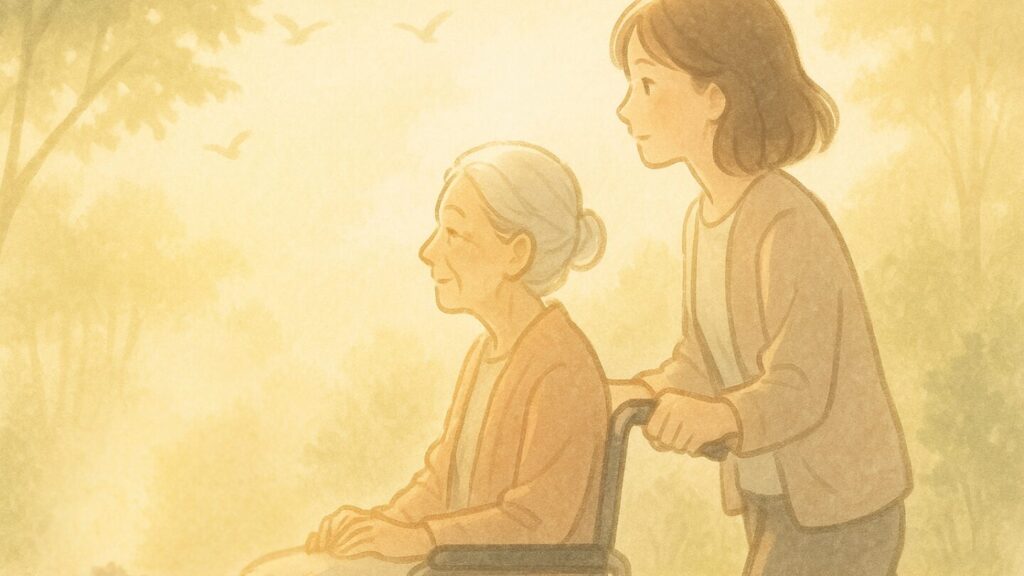
本人の表情、好きだったこと、笑顔や言葉
それが見えなくなってきたとき、介護する方の心にも「迷い」が生まれます。
今介護をしている、そのご高齢の方は、どれくらい“その人らしさ”が残っているのでしょうか?
- まだ表情の変化はあるのでしょうか?
- 好きなこと・嫌いなことは言えるのでしょうか?
もう何も言えず、表情の変化もよくわからない。
一緒に過ごしてきたけれど、この人の気持ちはよくわからなかった。
もしこのような状況であれば、迷いがあるのは当然です。
しかし、迷っている間にも時は過ぎてしまいます。
何もせずに時が過ぎてしまうことこそ、不安なことはないでしょう。
だから、今できることとして
せめて目の前にあるご飯を食べてと
相手の気持ちは分からないけれど
すすめてしまうこともあるのです。
「生きてるだけでいい」では、心が持たない
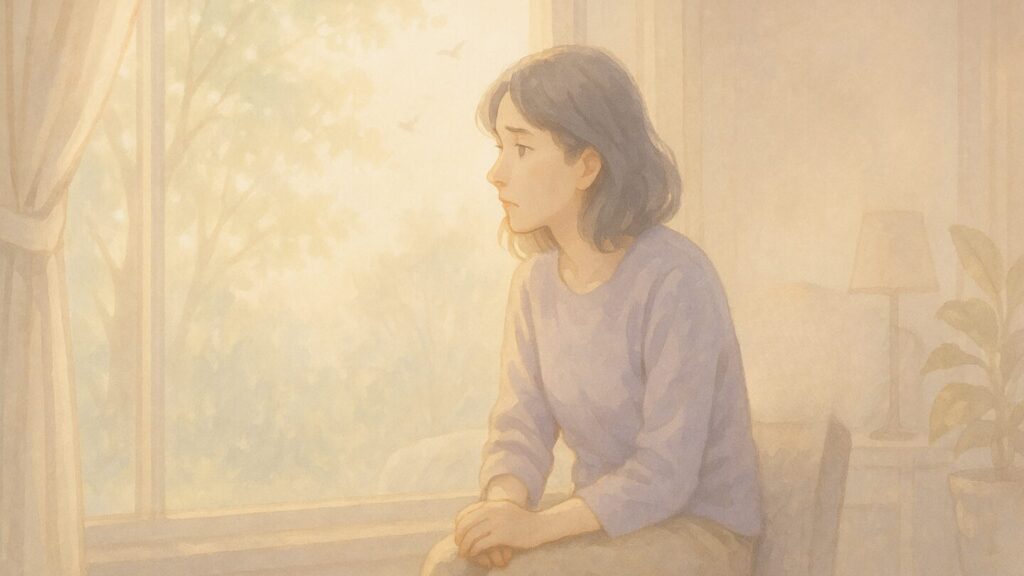
長生きしてほしい。
確かに、短いよりは長いほうがいいかもしれません。
しかし、“その人らしさ”がなく、生き続けることに意味を見いだすのは、難しいものです。
- 「生きているだけでいい」
- 「生きてさえいればいい」
この願いは本当に「その人」の願いなのでしょうか?
“その人らしい時間”を少しでも共有できたときの、あたたかさ

例えば、私たちがふるさとに帰省したり、旅行に行ったりするとき、「帰る時間」を決めるのは、私たち自身です。
家族に「もっといなさい」と言われても、私たちは自分のタイミングで帰りたいものです。
常に私たちは、自分のやりたいことを自分で決定しています。
それは、介護を受けている高齢の方も同じかもしれません。
ご高齢の方のペースに合わせることは本当に大変なときがあります。
でも、そのときのその方の笑顔を見たときに
(ちょっと大変だったけど)手伝ってよかった
そう感じることがありますよね
命の価値は「数字」では測れない

寿命があと1年延びても、心がそこにないなら…
医学の発展により、延命だけなら可能になりました。
ですが、延命と引き換えに、たとえば植物状態などで、「その人らしさ」が感じられない場合
そこに本当に生きている意味があるのかどうか・・・
その場にいる方々は判断できないでしょう。
これは極端な例ですが
- たとえば自分で排尿が難しくなり、膀胱留置カテーテル(排尿するための管)を入れている方が「一度でいいから、しっかりおしっこしたいなあ」とつぶやく。
- 腎機能の数値が下がってしまい、食事制限を受けている方が「好きなものを食べたいな」と話す。
医学的に正しいことを行っていたとしても
それによって“その人らしさ”が損なわれてしまうなら
長生きの価値を見出すことは難しくなるかもしれません。
それよりも“今日1日が満たされる”ことの方が、大切かもしれない

「じゃあそんなことを言うなら、その人に好きなことをさせて、寿命が短くなっても自由に生きて、周りのことも考えずに亡くなった方がいいのか?」
そんな声が聞こえてくるかもしれません。
大切な家族が、今まさに命の終着駅に向かっているという事実は、簡単には受け入れられないものです。
しかし、介護を頑張っているあなたやその周りの家族が受け入れられなかったとしても、時は過ぎていきます。
もし、明日、自分の命が終わると知ったなら、きっと今日という1日を大切に生きるはずです。
それと同じように、介護を受けているその人が、どのようにすれば満たされる1日を過ごせるかを考えてみることは、大切なことかもしれません。
もし明日尽きると思っていた命が、もう1日だけ延びたとしたら・・・
それは1日もうけたようなもの。
もう1日、楽しく過ごせばいいのではないでしょうか。
おわりに:「どう生きてもらうか」を考えるということ

- 命の長さを願うこと
- その人らしさを大切にしたいと思うこと
どちらも愛情のかたちなのだと思います。
正解はありません。
ただ、日々の中で私たちが悩んで、迷って、一生懸命に向き合ってきたということが、すでにひとつの答えなのかもしれません。
今日の笑顔
少しの会話
穏やかな眠り
そのすべてが、命を共にしているという証です。
この仕事に携わり、私も、まだ明確な答えにはたどり着けていません。
それでも、こうして誰かと“命について”考える時間があることが、少しだけ、心が軽くなるように思います。
そして、最後にお伝えしたいことがあります。
今、あなたが悩んでいるその状況は、あなたのせいではありません。
むしろ、ここまで本当によく頑張ってこられたあなたに、感謝の気持ちでいっぱいです。
どうか、あなたのそばにある時間が、あたたかく、穏やかに過ぎていきますように。

参考文献・参考サイト
本記事は筆者の現場経験をもとに執筆し、ChatGPT o3 を用いて、以下に示す厚生労働省発行資料との整合性を確認しました。
- 厚生労働省.令和4年度 人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査(社会保障審議会医療部会 資料2,2023 年 6 月2 日)mhlw.go.jp
- 厚生労働省.「人生の最終段階における医療」の決定プロセスに関するガイドライン(改訂版)関係資料(2017 年)mhlw.go.jp
- 厚生労働省.人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査(統計一覧ページ)(最新アクセス 2025-06-18)mhlw.go.jp
- 厚生労働省.人生の最終段階における医療・介護 参考資料集(2023 年版)mhlw.go.jp
- 厚生労働省.在宅医療・介護連携推進事業の手引き ver.4(2024 年)mhlw.go.jp