はじめに
ケアマネとしての難しさを感じることのひとつに、
サービスが必要と感じる方に、うまく受け入れてもらえない
というものがあります。
たとえば─
客観的に見れば生活は安定していないのに、介護しているご家族が否定されたように感じ、頑なに話し合いに応じてくれないケース。

介護保険のサービスは利用したいです。
でも、なんかできなくて……もう少し私が頑張れば、なんとかなると思うし、そのほうがお父さんもいいんじゃないかなって。
サービスが必要と理解していても、「使うことは親を見捨てること」と思い込み、極限まで自己犠牲を払ってしまうケース。
こうした例は枚挙にいとまがありません。
ですが、誰しも多少は似た感覚を持つため、「わからなくはない」と思う方も多いでしょう。
しかし、不思議なことに、同じような気持ちを抱えても、サービス利用に踏み切れる人と、そうでない人がいます。
在宅で介護をしていると、周り──たとえば他の家族や職場──に気を使いながら、自分の働く環境や生活スタイルを介護に合わせて変えていくことになります。
「仕事」も「介護」も両立させようと頑張る中で、
「どうして自分だけが……」
という怒りや、理由の分からない悲しみを感じることもあるでしょう。

「え、それほど苦しいなら、サービスを使えばいいのでは?」と思いますよね。
しかし、先ほど紹介したように、それでもサービスを使おうとしない方は少なくありません。
実はこの違いの背景には、「介護する人とされる人との境界線のあいまいさ」が関係しています。
今回の記事では、この“境界”という視点から、介護中に生じる怒りや悲しみのメカニズムを紐解いていきます。
読み進めることで、「自分の生活」と「在宅介護」の線引きが少しずつできるようになるはずです。
そして「どうして私だけが……」という思いも、きっと軽くなっていくでしょう。
- 介護で湧く「怒り・悲しみ」の背景には、境界のあいまいさがあります。
- 10問セルフチェックで、自分の傾向(同一化/エンメッシュメント/共依存)を可視化できます。
- 解決の第一歩は、一人で背負わない仕組み化(ケアマネジャーに相談やサービス活用)です。
この記事は、主任介護支援専門員の資格を持つ現役ケアマネジャーが執筆しています。在宅介護でお悩みの方に信頼できる情報をお届けすることを目的としています。
介護と自分の境界、ちょっと確認してみませんか?
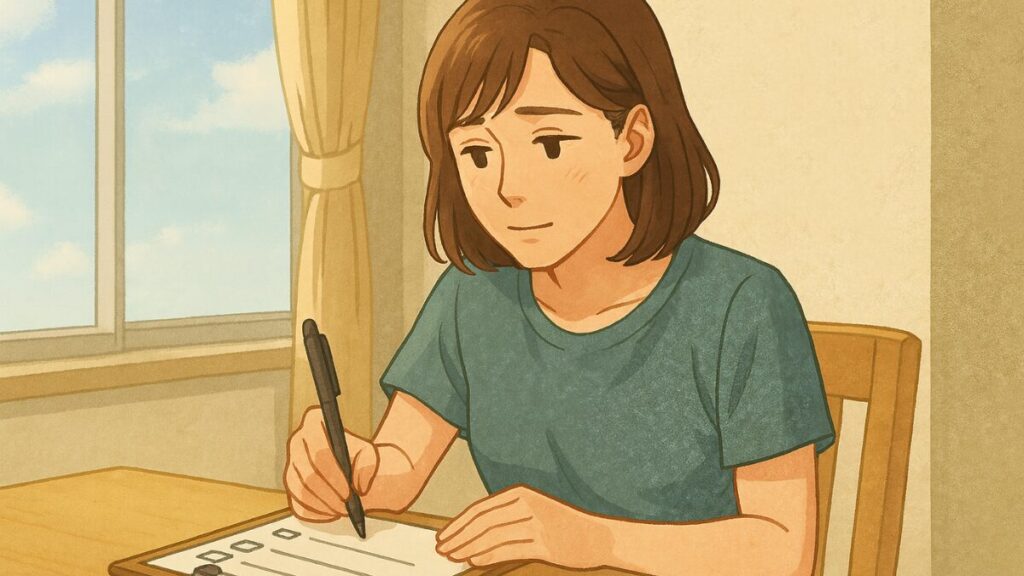
ではここで、あなたの状態を振り返ってみましょう。
以下は「介護をしている中で、境界があいまいになりやすいサイン」をまとめた10項目です。
それぞれの問いに「はい」「いいえ」で答え、「はい」の数を数えてみてください。
※これは診断ではなく「気づき」のためのチェックです。
「どちらでもない」とき、「いいえ」にして見逃すよりも、「はい」として進んでみましょう。
設問リスト(1〜10)
在宅介護で「境界があいまい」になっていないか?セルフチェック
これは診断ではなく 「気づき」 のためのチェックです。
迷ったときは「いいえ」にして見逃すより、「はい」に寄せて考えてみましょう。
採点の目安
- 0〜3個:境界のあいまいさによる負担は比較的少ない状態です。ただし安心しきらず、早めに小さな工夫やサービスの活用を意識するとよいでしょう。
- 4〜6個:介護による心理的な負担がかなり強くなっています。「怒りや悲しみ」を日常的に感じやすい段階であり、自分の時間を確保したり、家族や専門職に支援を求めることが大切です。
- 7〜10個:境界がかなり曖昧になり、自己犠牲が強くなっている可能性があります。強い怒りや悲しみ、孤独感につながりやすいため、信頼できる人や専門機関に相談し「一人で背負わない工夫」を真剣に考える必要があります。
心理の視点から見る「境界があいまいになる」しくみ

そもそも 「境界があいまいになる」とはどういうことか を見ていきましょう。
境界があいまいになるというのは、よく分かるような、でもはっきりとは説明しにくい話ですよね。
私たちは誰でも、自分の中に「見えないけれど確かにある境界」を持っています。
例えば、親しい相手と会話をしていても、距離が近すぎると「ちょっと近いかな」と感じることがあります。
けれど、夫婦や親子のような関係では、境界が薄くなっているため、同じ距離感でも不思議と違和感を覚えないこともあります。
つまり、境界があいまいになることは誰にでも起こりうることです。
そして、そのような状態では
- 同一化
- エンメッシュメント
- 共依存
といった傾向が現れることが知られています。
その傾向が強く出すぎてしまうと、在宅介護では自分を苦しめる状況につながります。ところが本人自身は気づきにくいのです。

ちょっとごめんね。
今回は「怒り」とか「悲しみ」の対処法の話じゃないの?
いったい何の話になってきたの?
今回の記事は、介護で感じる「怒り」や「悲しみ」を抑えるテクニック(多くの解説が「怒りは二次感情」「6秒我慢」といった対処法)を紹介するのではなく、その根本原因に焦点を当てています。

怒りや悲しみの背景のひとつに、「境界のあいまいさ」があります。
これに向き合わないと、繰り返される怒りや悲しみを軽くすることがそもそも難しいのです。
同一化 ― 「自分と相手の気持ちを同じだと思ってしまう」

定義
心理学でいう「同一化(identification)」とは、本来は子どもが親を手本にして成長するように、他者の考えや感情を自分の中に取り入れるプロセスのことです。
しかし介護の場面では、防衛機制のひとつとして「相手=自分」と感じすぎてしまい、境界が曖昧になることがあります。
(セルフチェックでいうと、1番・2番の質問がこれにあたります。)
在宅介護の例
- 「今日は入浴したくない」と言う親に、「いや、本当は入りたいに決まっている」と自分の判断で強引に介助を進めてしまう。
- 「私がいないとこの人は何もできない」と思い込み、自分の外出や休息を諦めてしまう。
- 本人が「今日は食べたくない」と言っているのに、「いや、本当は食べたいに決まっている」と思い込み、無理に食べさせてしまい、拒否されると「どうしてわかってくれないの」と怒りが湧いてくる。
- 親がつらそうにしていると「私ばかりが平気でばかりいられない」と感じて休めなくなり、結果的に疲れ切ってしまい、「どうして私ばかり」と悲しくなってしまう。
- 本人が「今日は外に出たくない」と言うと、「私も一緒にいなければ」と考えてしまい、外出の機会を失い、「自分の生活まで制限されている」と悲しくなる。
- 親が「まだ大丈夫」と言うと、「親がそう言っているのだからきっと大丈夫なのだろう」と思い込み、介助を後回しにしてしまう。結局あとで手がかかることになり、「なんで素直に言ってくれないの」と怒りが湧いてくる。
一見すると献身的に見えますが、実際には 「自分がいなければ」という思い込みで責任を過剰に背負い、怒りや悲しみを抱きやすくなる 状態です。
エンメッシュメント ― 「気持ちや生活が絡み合いすぎて、離れられなくなる」
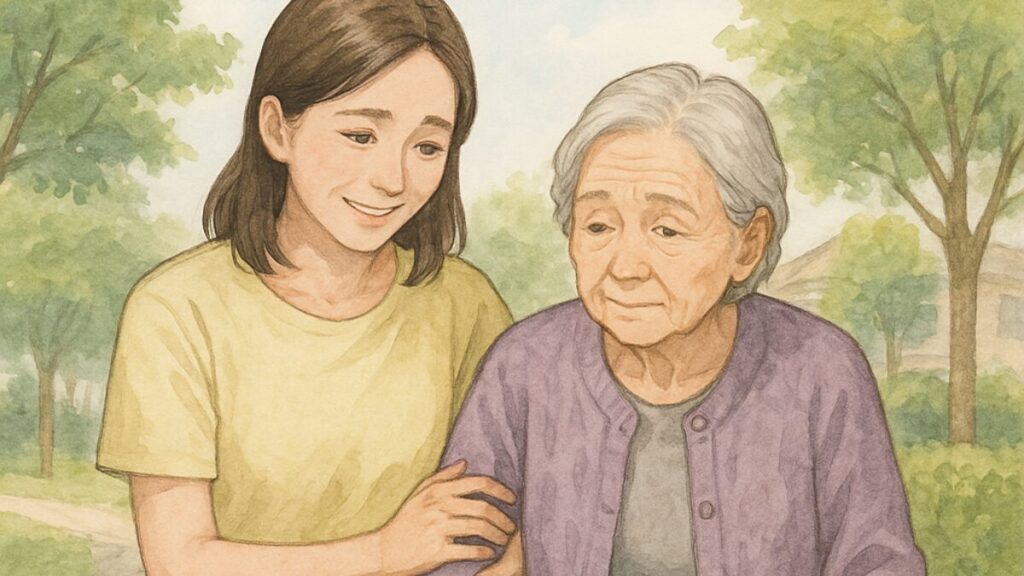
定義
エンメッシュメント(enmeshment)とは、家族心理学で使われる用語で、家族や親密な関係の中で心理的な境界が曖昧になりすぎ、互いの感情や行動が過剰に交錯してしまう状態を指します。
介護の場面では、相手の感情や生活を自分のものと同じように感じ取りすぎてしまい、「自分と相手の区別」がつきにくくなることがあります。
(セルフチェックでいうと、3番・4番・5番・6番の質問がこの傾向にあたります。)
在宅介護の例
- 親が「食欲がない」と言えば、もう親が亡くなるかもしれないと不安になり、自分も気持ちが沈んで一日中暗い気分になる。
- 自分の用事よりも常に親の予定を優先し、友人や社会とのつながりが薄くなり、介護離職も考えてしまう。
- 親が「腰が痛い」と言うと、自分まで痛い気がして外出を控えてしまい、「自分の生活まで縛られている」と悲しくなってしまう。
- 親が不機嫌になると「自分が悪いのでは」と思い込み、必要以上にへりくだってしまい、「どうして私ばかり我慢しなければ」と怒りが湧いてくる。
- 親の予定に合わせるために、自分の健康診断を先延ばしにし続けてしまい、「私のことを誰も気にしてくれない」と悲しくなる。
- 家の中の雰囲気が常に親の機嫌に左右され、笑顔なら安心し、不機嫌だと家全体が暗くなり、「家族の暮らしが全部振り回されている」と怒りが込み上げてくる。
- 介護以外の会話をしていても、結局親の話題になってしまい、「自分の時間や気持ちがなくなってしまう」と悲しくなる。
このように、相手の気持ちや生活に過剰に巻き込まれることで、自分自身の生活や感情が相手に左右され、怒りや悲しみを抱きやすくなる のです。
共依存 ― 「介護することが自分の存在価値になってしまう」

定義
共依存(codependency)とは、本来は依存症の領域で使われる用語ですが、介護にも当てはまります。
相手に依存されることで自分の価値を感じ、同時に自分もその関係に依存してしまう状態です。
介護者にとって「世話をしている自分」が自己肯定感の拠りどころになり、他人の介護を受け入れることが難しくなります。
(セルフチェックでいうと、7番・8番・9番・10番の質問がこの傾向にあたります。)
在宅介護の例
- 協力してもらえないと「どうして自分ばかりが」と不満や怒りが湧き、協力しても「自分を差し置いて勝手に介護するな」と感じ、家族との関係がぎくしゃくしてしまう。
- 「自分がいなければ」と必死に介護を続け、それで私は大変素晴らしいことをしているのだと自分で美化してしまい、周りに理解されないと怒りが湧いてくる。
- ケアマネや医師からサービスを提案されても、「他人に任せたら心配だ」と考え、受け入れを拒み、後で疲れ果てて悲しくなってしまう。
- 介護以外の話題がほとんどなくなり、友人と会っても自然と介護の愚痴や武勇伝ばかりを話してしまい、「結局わかってもらえない」と孤独を感じて悲しくなる。
- 介護中心の生活になり、趣味や楽しみを忘れてしまい、夜寝る前に「今日も介護だけで終わったな…」と悲しくなる。
このように、介護そのものが自分の価値や存在理由になってしまうと、協力しても不満、協力されなくても不満という矛盾が生じるのが、共依存の大きな特徴です。
まとめ:境界があいまいになると怒りや悲しみを生むメカニズム
在宅介護では、気づかないうちに「介護する人」と「介護される人」の境界があいまいになりやすくなります。
その現れ方にはいくつかのパターンがあり、心理学では同一化・エンメッシュメント・共依存と呼ばれていることを先ほどお伝えしました。
これらはどれも、「介護者が相手との境界を失い、自分の生活や感情を後回しにしてしまう」ことが根っこにあります。
ただし、境界があいまいになること自体は誰にでもある自然なことです。
むしろ適度なあいまいさは、相手との共感を深め、強い信頼関係を築くきっかけにもなります。
問題は、そのあいまいさが過度になってしまうことです。
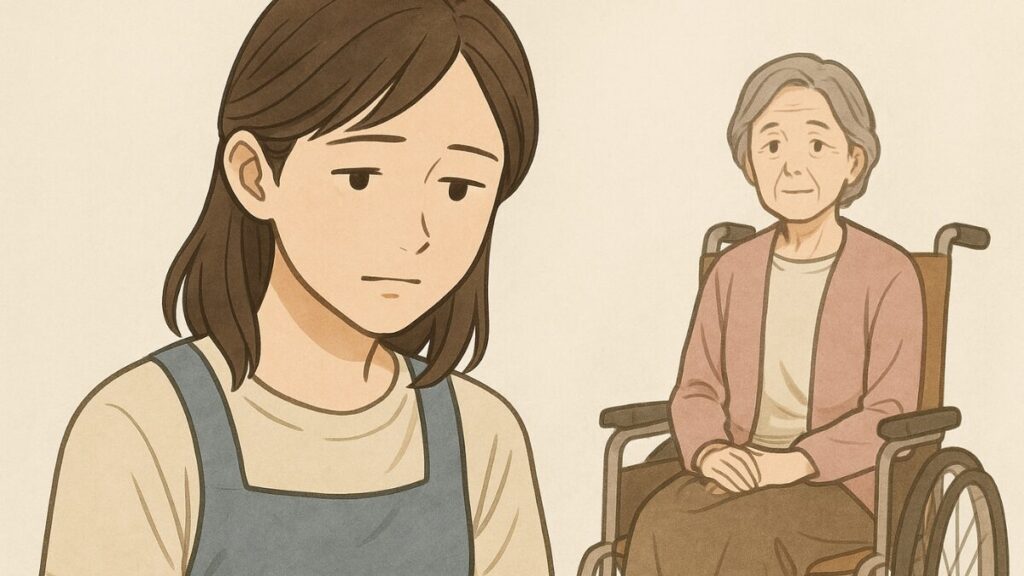
相手の状況を自分のことのように背負い込んでしまうと、知らず知らずのうちに苦しさを抱えてしまいます。
その結果、介護者の心には「理解してもらえない」と怒りや悲しみといった強い感情が生まれるのです。
怒りや悲しみは「あなたの心が弱いから」ではありません。
それは境界があいまいになったときに自然に生じるサインなのです。
この仕組みを理解することが、介護を少し楽にし、「自分の生活」と「介護の生活」を切り分ける第一歩になります。
そして、その一歩が、これからの介護を続けていくうえであなた自身を守り、相手との関係をより良くする助けにもなります。
境界を取り戻し、介護と自分を大切にするために

どうしようもなく沸き起こる怒り、あるいは悲しみは、
「これまで自分の境界を溶かしてまでも相手のことを理解しようとして、同じように苦しんだ結果の果てに起こるもの」だとわかりました。
生きる大変さを人の倍背負い、介護を続けたあなたが、もう一度自分を取り戻すためには、あなたが勇気を持ってあなたのために行動するしかありません。
私は、心理カウンセラーではありませんが、これまでケアマネジャーとしてたくさんの境界があいまいになり、疲れ果てたご家族様を見てきました。
そして伝え続けたことは、 「勇気を持ってサービスを使ってほしい」ということでした。
「たったそれだけか?」と思うかもしれません。
でも、サービスを利用することで、介護を受ける相手は快適になり、介護するあなたにも忘れていた自分の時間が戻ってきます。
その小さな変化が、あなたの心に余裕をもたらし、新しい境界をつくり直すきっかけになります。
- デイサービスは利用時間は長く感じるかもしれません。しかし、1日24時間で考えれば、ご家族と一緒にいる時間のほうが長いです。
- ショートステイでは、利用している間は、本当に忘れていた平穏が訪れるでしょう。
とはいえ、境界があいまいになっている時には、素直に受け入れるのが難しいこともよく知っています。
だからこそ、使うためには「勇気」が必要です。少し大げさに聞こえるかもしれませんが、実際に必要なのです。
もしどうしても一歩を踏み出せないときには、せめて「自分だけの時間」を持ってください。
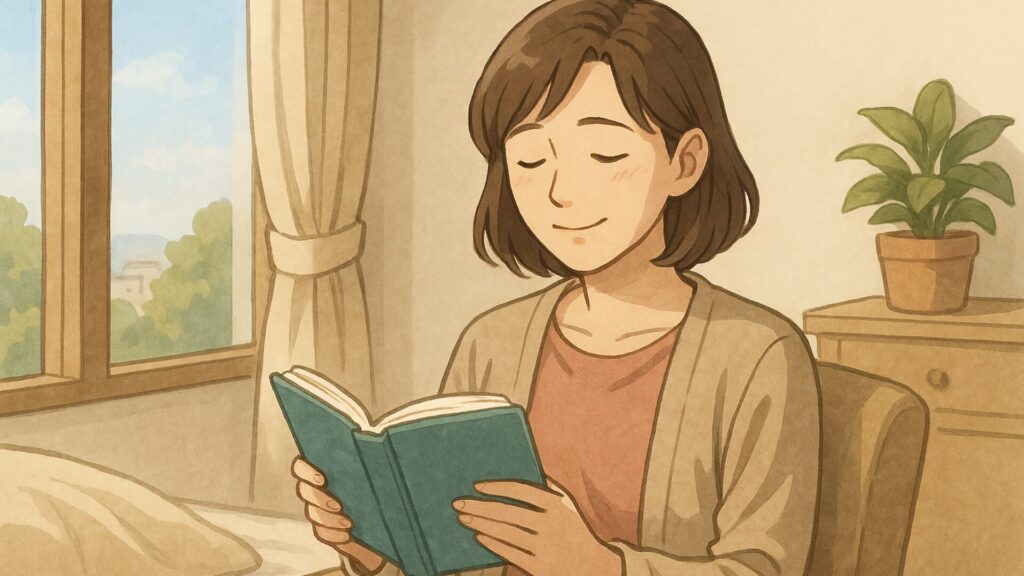
- 好きな本を読む。
- 好きな飲み物を味わう。
ほんの小さなことでもかまいません。
相手と融合してしまって見失いかけていた「自分の声」に、耳を傾けてほしいのです。
きっと何か聞こえてくるはずです。
そうして少しずつ自分を取り戻し、少しずつ行動して、境界を整えていくことで、ご家族様とも新しい関係が築かれていきます。
勇気を持って、あなたと向き合い、勇気を持って休んでください。
あなたはきっと大丈夫です。
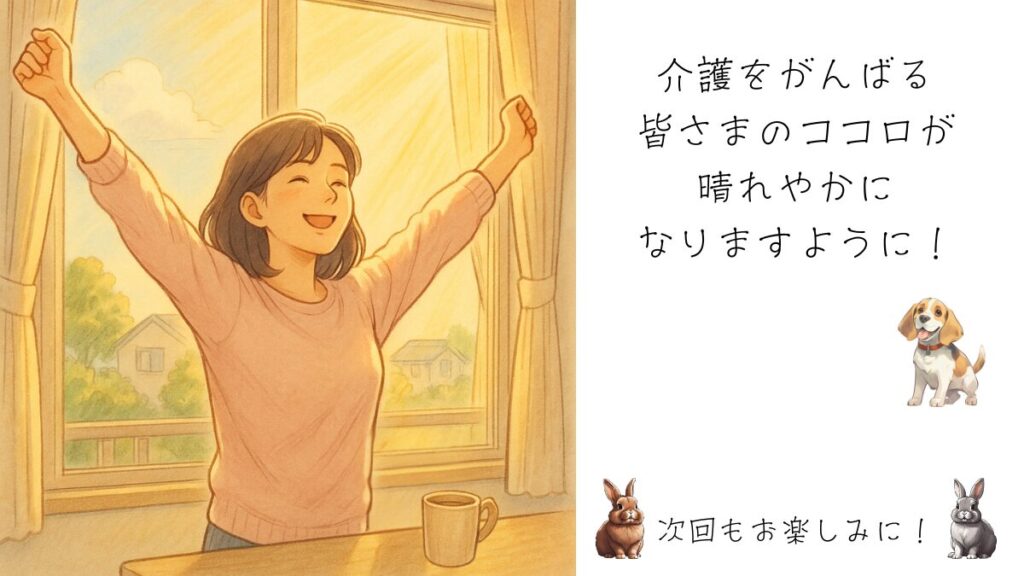
迷ったらまずここに相談
地域包括支援センターは、市区町村が設置する総合相談窓口です。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などが、 介護の悩みや制度利用、権利擁護、地域の支援体制づくりまで初期から継続的に伴走します(介護保険法に基づく中核機関)。 まずはお住まいの地域の窓口を確認し、相談方法・受付時間を電話で確認しましょう。
- 近くの窓口を探す: 介護サービス情報公表システム(地域包括支援センター検索)
- 市区町村の相談窓口一覧の入口: WAMNET「介護の地域窓口」
- 仕事と介護の両立: 厚労省「介護離職ゼロポータル」
参考文献(公的資料・学術論文)
※本記事の内容は、GPT-5 Thinking Deep reserchによるクロスチェックで、以下の一次資料・公的資料・査読論文と整合性を確認しています(最終アクセス:2025-08-31)。
厚生労働省 老健事業推進費等補助金調査研究報告書『介護・労働施策等の活用による家族介護者支援に関する調査研究』(令和3年)murc.jp
加藤伸司「家族介護の視点から」『認知症のケア 各論3』(認知症介護研究・研修仙台センター, 2019)tyojyu.or.jp
任 賢宰「認知症の人を支える家族介護者への心理的支援の必要性」旭川市立大学コミュニティ福祉学科 ケアスル介護コラム(2024年)asahikawa-u.ac.jp
厚生労働省 「高齢者虐待防止法に基づく養護者による高齢者虐待の対応状況(平成18年度~令和3年度)」(令和4年)※公明新聞による紹介komei.or.jp
メディカル・ケア・プランニング「罪悪感を抱いていませんか?施設入所に、罪悪感を抱いてしまう方へ」気になる介護(2020年)mcp-net.jp
休職に関するお悩み解決サイト「介護者のメンタルヘルスの問題について」(2023年)kyuushoku.comkyuushoku.com
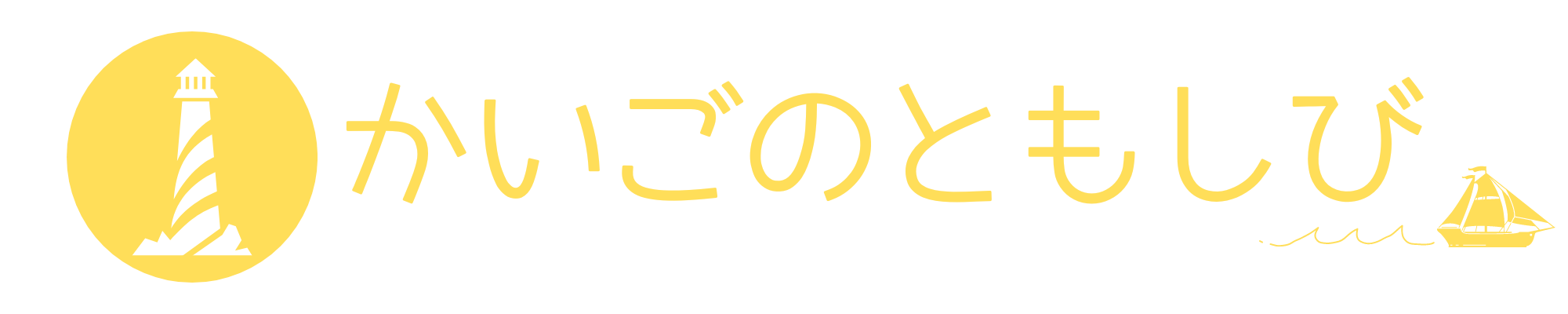
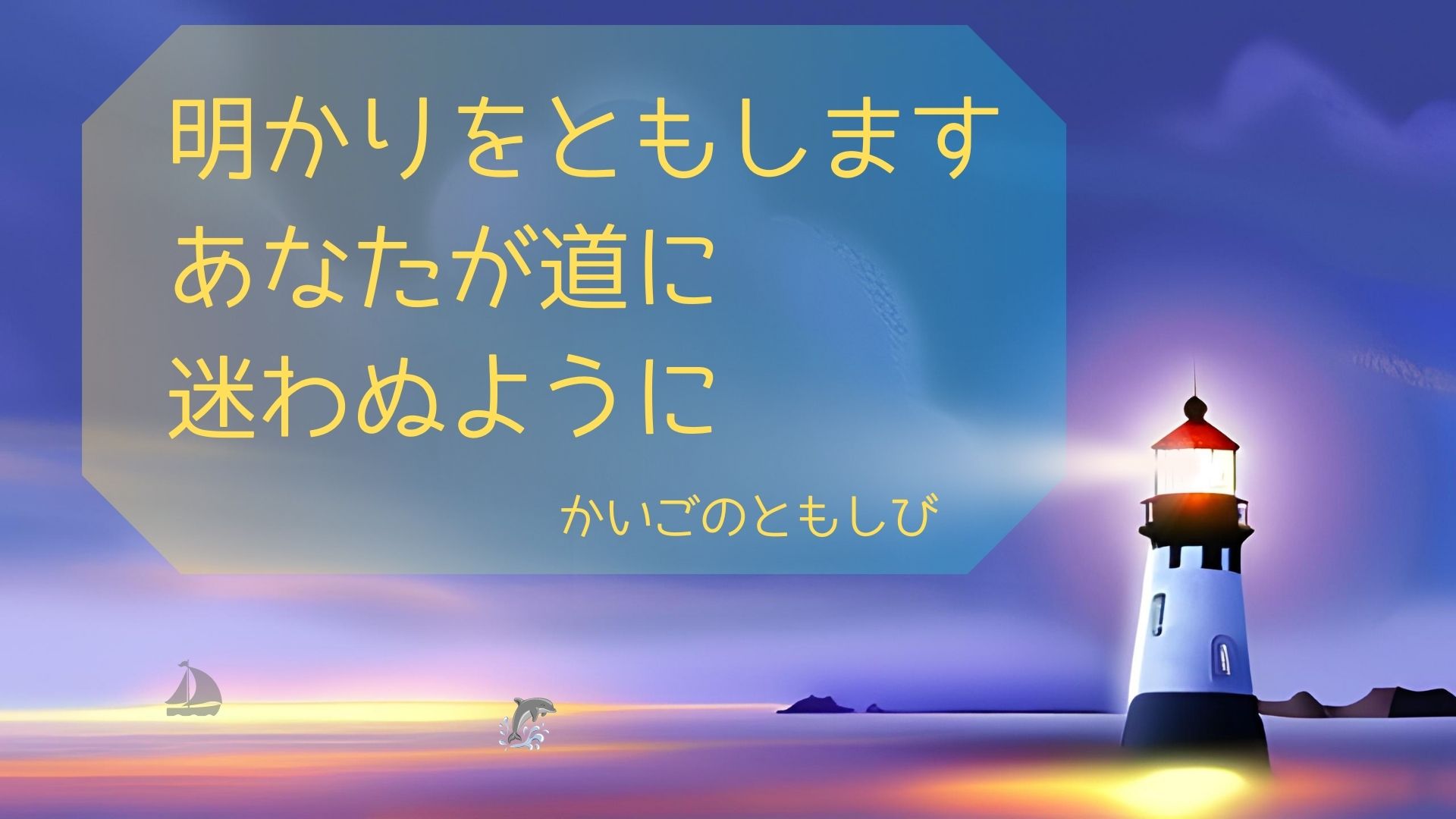

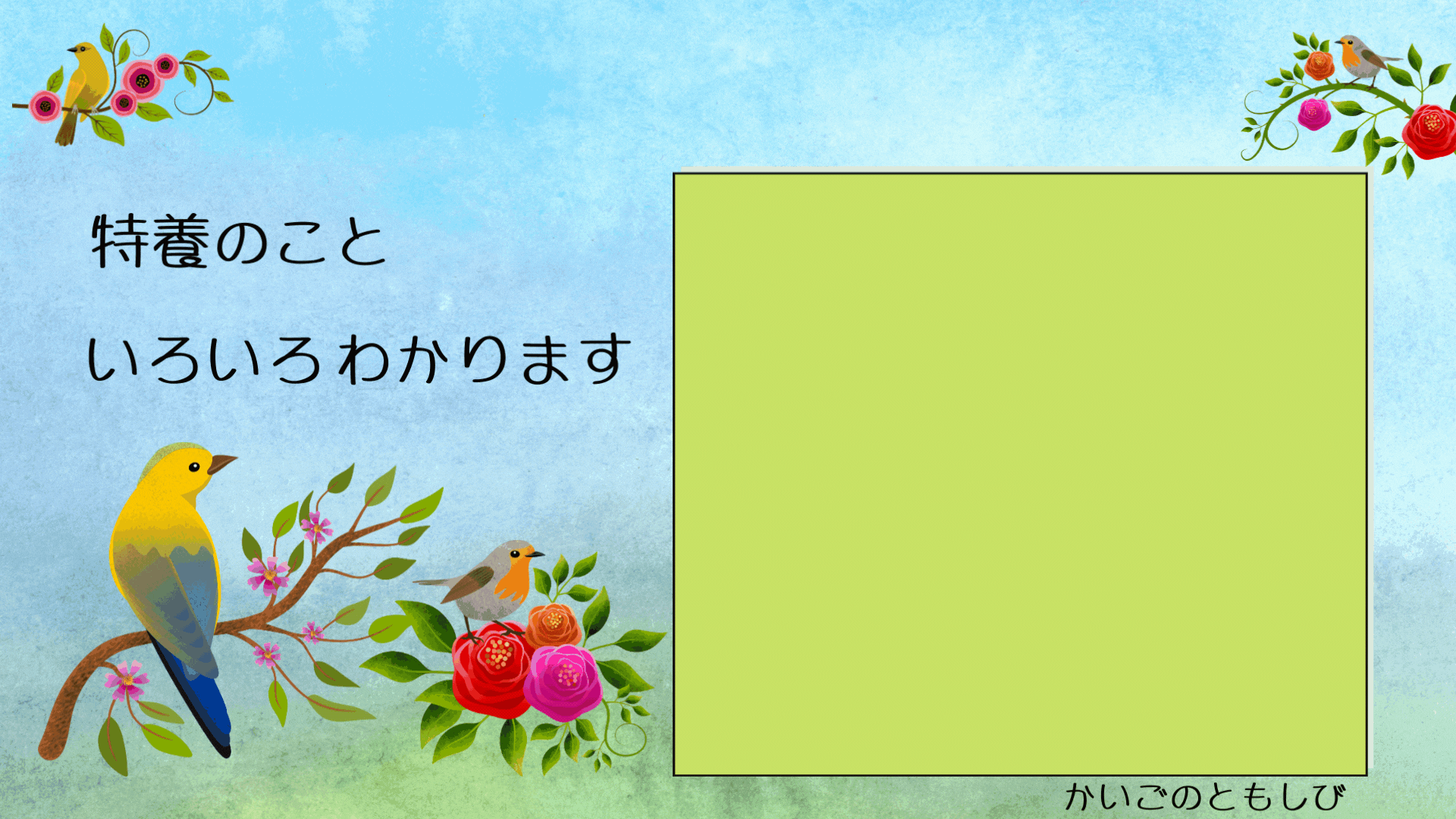

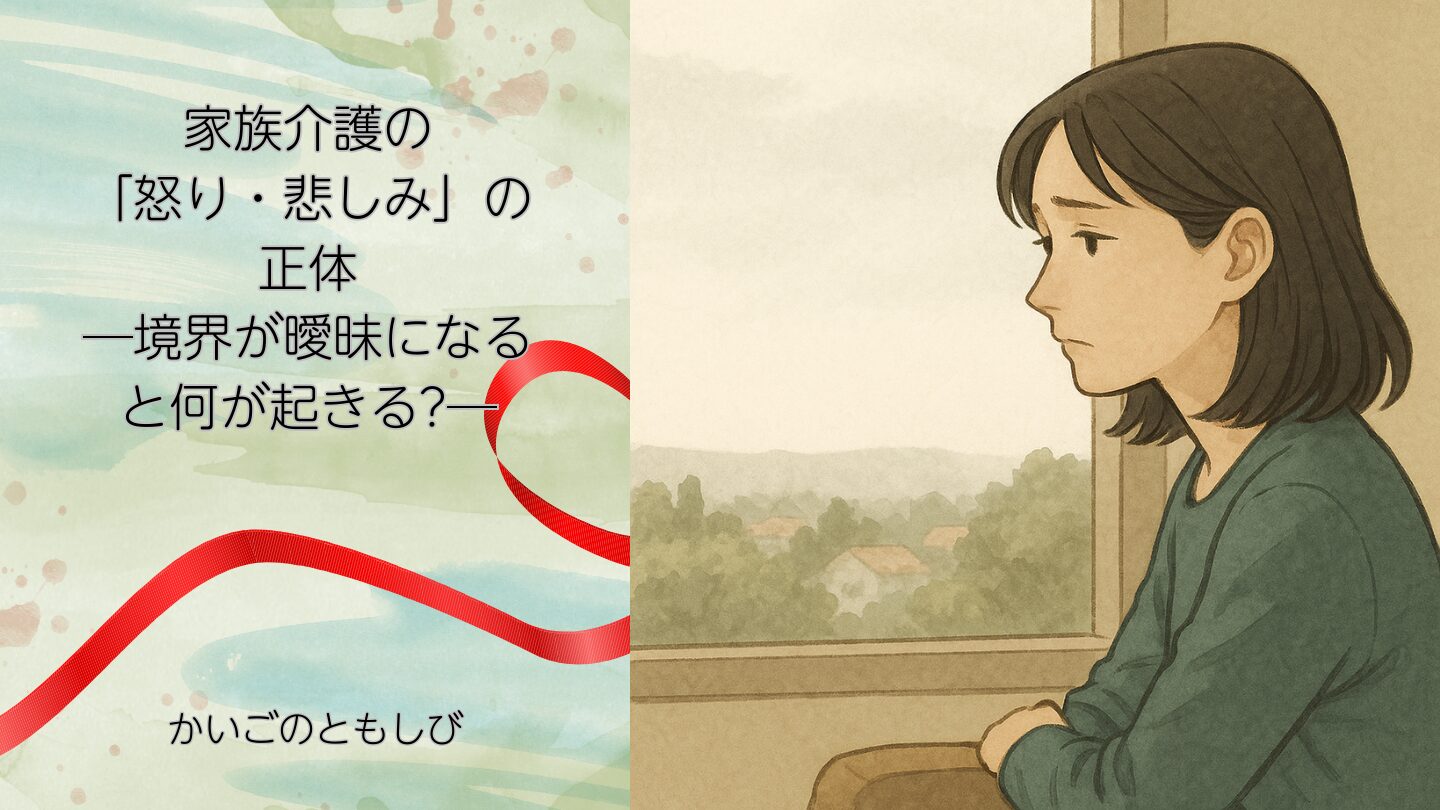
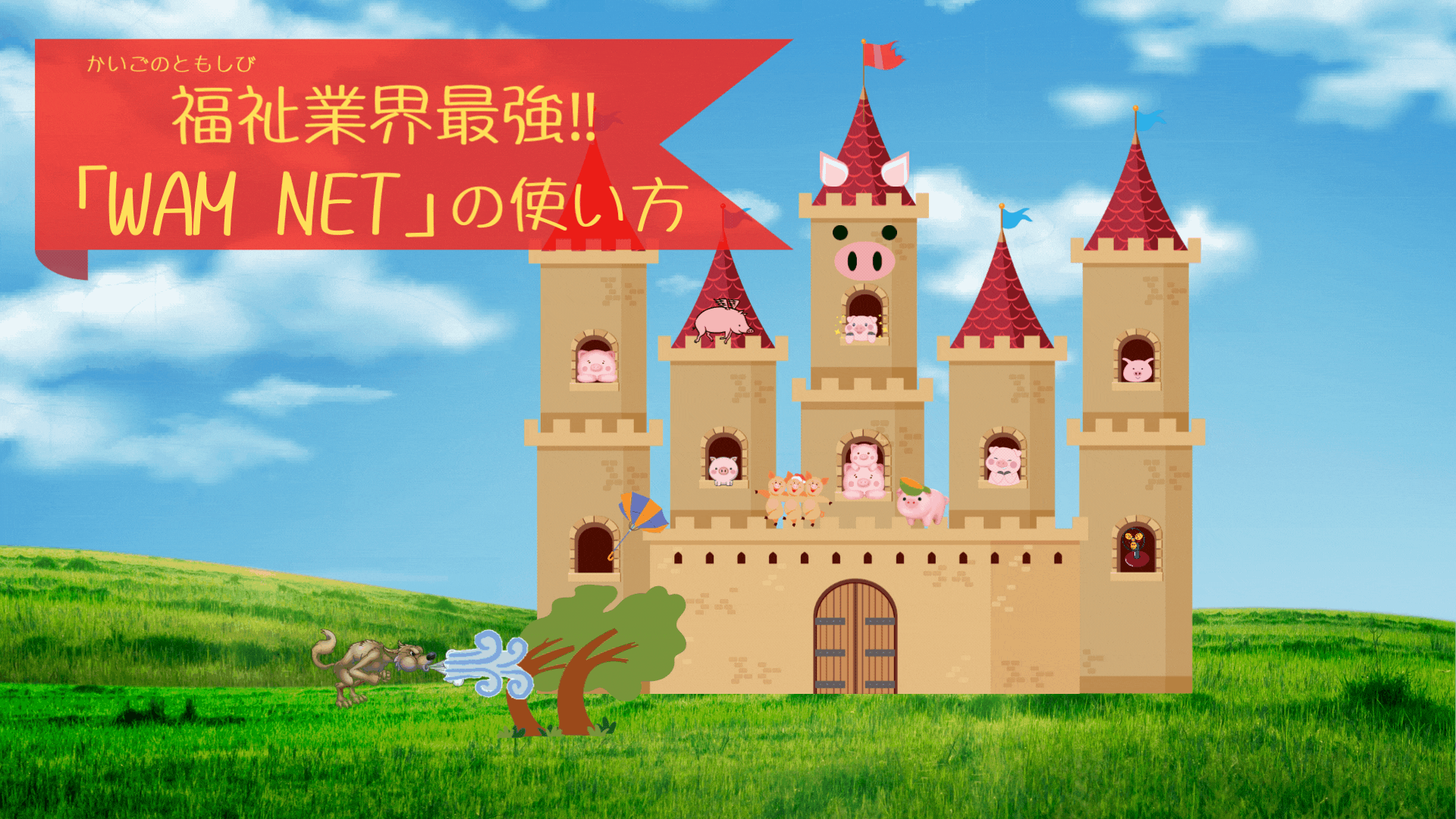





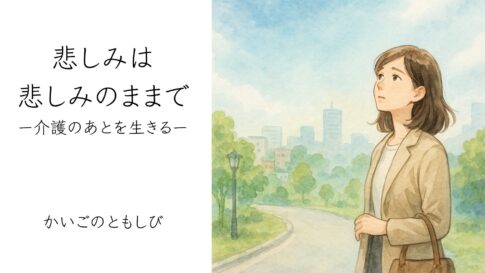
おれはちゃんとお世話しているよ。
今朝だって、おふくろにパン粥と(即席の)コーンスープを食べさせた。
十分出来てるだろ。これまでもそうだったし。
どうしてサービスを使う必要があるんだよ!
もう仕事だからそろそろ帰ってくれ。